こんな疑問を解決する記事を書きました。
2024年4月から無添加表示が禁止されたと聞いて、驚くと同時に混乱している方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では無添加表示の禁止について、具体的な変化や理由、対処法を詳しくお伝えしていきます。
この記事を読めば、実際にどんな変化があったのか、今後どんなことに気をつけていけばいいのかが分かってスッキリしますよ。
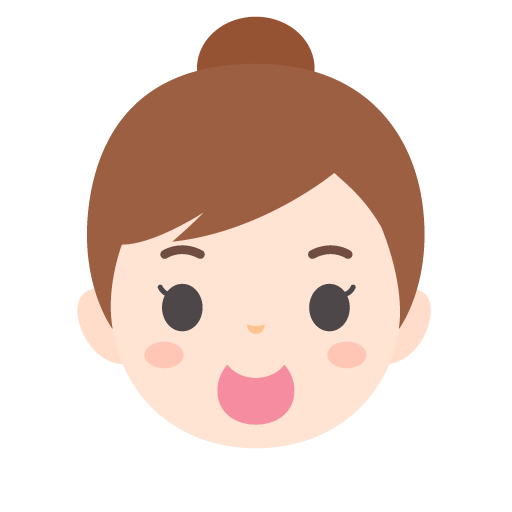
ちなみに私は無添加・オーガニック歴9年。添加物を気にしすぎて疲れた過去もありましたが、今は自分なりの基準を決めたことで、食事を心から楽しんでいます。
そんな私が無添加生活を送る中で感じた、実際の変化や感想なども交えてお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください!
※取り急ぎ今後の対応が知りたい方は、『無添加表示の禁止による実生活への影響』に進んでくださいね。
無添加表示は禁止されたのか?

結論から言うと、無添加表示は禁止されたわけではありません。
ただ「誤解を招きかねない表現」を使わないよう、一定のルールが設けられたんです。
たとえば食品パッケージに単に「無添加」と書かれていた場合、見た人は添加物が一切使われていないと受け取りやすいです。
しかし実際は特定の添加物が使われていないだけで、ほかの添加物は使用されていることがよくありました。
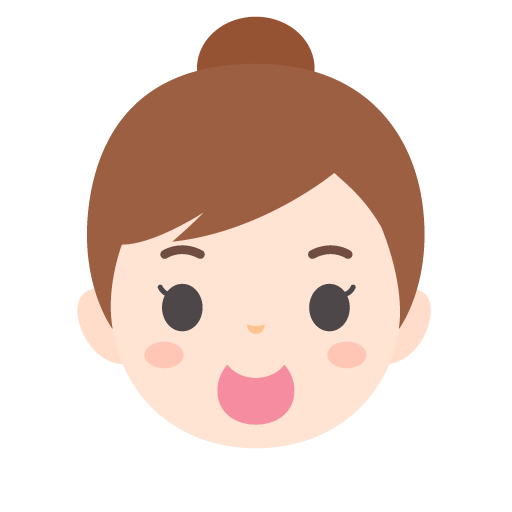
つまり表示を見た人が事実を誤認して買ってしまうケースが、普通にあったんですね。
そのため単に無添加と表示するのは止めて、「〇〇無添加」と分かりやすく表示するようにしましょうとなったワケです。
そして2024年4月からは、上記を含む10項目のルールが適用されるようになりました。
詳しくは『無添加表示はどう変わったのか』の項でお伝えするので、まずは無添加の表示がまったく禁止になったのではなく、一定のルールができたと理解しておきましょう!
無添加表示が禁止された理由

無添加表示が禁止された理由をひとことで言うと、消費者に誤解を与える表示が多かったからです。
たとえば上記でもお伝えしたように、一部の添加物を使っていないだけなのに、「無添加」と表示することで消費者に完全無添加と誤解させるケースなど。
このような表示が多かった背景には、無添加に対する「安全」「健康」といった良いイメージがあります。
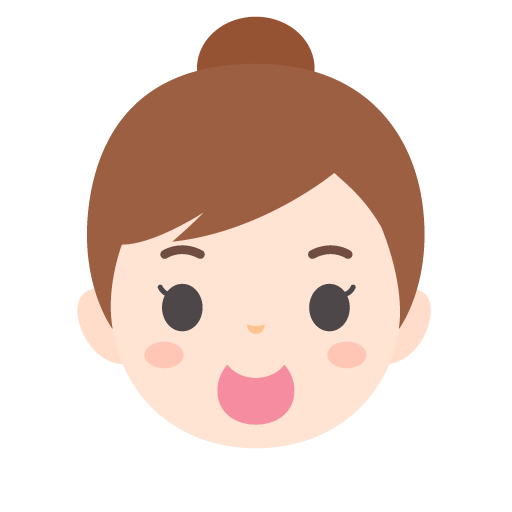
「無添加」と表示しておくと商品が売れやすかったから、食品業者もよく使っていたということですね。
しかし誤解を与える表現があまりに多かったため、ついに国による規制が入ったわけです。
そして今回、新しい表示ルールができたことで、より正確な情報が手に入るようになりました。
まとめると無添加が危険だから表示禁止になったのではなく、今まであまりに自由に表示されていたから、厳しいルールを作ったということです。
もし今回のことで『無添加は危険なの?』と不安に感じた方は、以下の記事で詳しくお話しているので、よければ目を通してみてください!

無添加表示はどう変わったのか

消費者庁の発表した食品添加物の不使用表示に関するガイドラインでは、10項目のルールが定められました。
おおまかな内容は無添加に関するあいまいな表示や、誇張した表現をなくすことです。
たとえば単に無添加と表記することや、効果をうたう表現、過度に強調されたデザインなどが禁止になりました。
また無添加表示の定義も明確になり、いい加減な使い方ができなくなったんです。
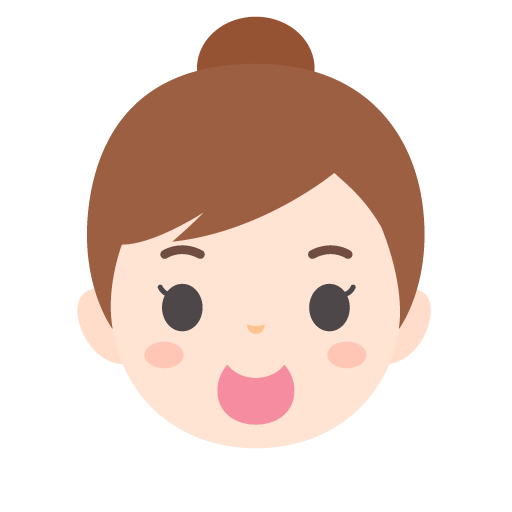
無添加表示の定義はかなり厳しめなので、今後は無添加と表示する食品が減っていくことが予想されます。
そんな中、もし無添加と表示をしている食品があったら、相当本気でこだわっている(または法律違反かも)ということですね。
『10項目の詳細な内容』については後ほどお伝えしますので、今回の規制によって無添加表示はかなり厳格になったことを、まずは理解しておきましょう!
無添加表示の禁止による影響

無添加表示のルールが厳しくなったことで、私たちは食品に使われている添加物について、より正確に把握しやすくなりました。
ただしこの変化は今まで「無添加」の表示を頼りに食品を選んでいた人にとっては、少し不便に感じるかもしれません。
実際、無添加の表示が減るとなると、自分で原材料欄などを見て、使われている添加物を確認する必要があります。
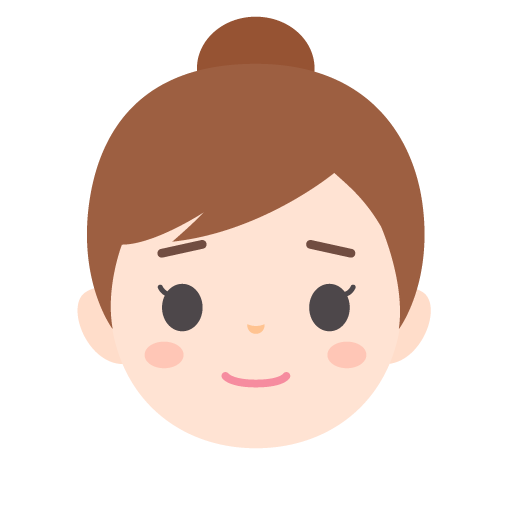
慣れないうちは訳のわからない名称や、物質名に戸惑うこともあるかもしれません。
それでも添加物をなるべく避けたいなら、最低限の知識を身に付けておくことをオススメします。
ひとまず以下の2つの記事を読んでおけば大体の知識は得られるので、よければ目を通してみてください。
また「自分で原材料欄などを確認するのは大変……」という方は、無添加にこだわる食品業者を利用するのもオススメです。
以下の記事では『無添加食品の宅配ランキング9選』を比較してご紹介しているので、よければチェックしてみてください!

無添加表示の具体的なルール一覧
以下に消費者庁が発表した食品添加物の不使用表示に関するガイドラインで発表された、10項目のルールをまとめたので参考にしてみてください。
| 項目名 (注意すべきこと) |
内容 | 具体例 |
| ① 単なる「無添加」 の表示 |
「何が無添加なのか」 を明記する |
✕無添加 ◯保存料無添加 ◯着色料不使用 |
| ② 食品表示基準に 規定されていない 用語を使用した表示 |
人工・合成・化学・天然 などの言葉を使わない |
✕人工甘味料不使用 ✕合成着色料無添加 ✕化学調味料不使用 |
| ③ 食品添加物の使用 が法令で認められて いない食品への表示 |
使ってはいけない添加物を わざわざ不使用と言わない |
✕清涼飲料水に 「ソルビン酸不使用」と表示 →そもそも使用禁止 |
| ④同一機能・類似機能 を持つ食品添加物を 使用した食品への表示 |
同じような機能をもつ添加物 を使っている場合は、 「〇〇無添加」と表示しない |
✕日持ち向上効果のある 「酸化防止剤」を使っているのに、 「保存料無添加」と表示 |
| ⑤ 同一機能・類似機能 を持つ原材料を使用した 食品への表示 |
同じような機能をもつ原材料 を使っている場合は、 「〇〇無添加」と表示しない |
✕日持ち向上効果のある 「しらこたん白抽出物」を使って いるのに、「保存料無添加」と表示 |
| ⑥健康、安全と 関連付ける表示 |
「無添加=健康・安全」 などの印象を与える表示 をしない |
✕発色剤不使用だから安全 ✕保存料無添加なので健康的 |
| ⑦ 効果・効能を連想 させる表示をしないこと |
何らかの効果・効能がある 印象を与える表示をしない |
✕無添加だから美味しい ✕無添加なので環境に優しい |
| ⑧ 食品添加物の使用が 予期されていない食品 への表示 |
添加物が使われない食品に、 わざわざ無添加と表示しない |
✕ミネラルウォーターに 「保存料無添加」と表示 →そもそも使われない |
| ⑨ 加工助剤、 キャリーオーバー として使用されている 食品への表示 |
加工助剤やキャリーオーバー として添加物が使用されている 食品に、無添加と表示しない |
✕せんべいの原材料である醤油に 保存料を使っているのに、 せんべいに「保存料無添加」 と表示 |
| ⑩ 過度に強調された 表示 |
無添加であることを、 過度に強調して表示しない |
✕商品のあらゆる場所に、 過度に目立つ色やフォントで 「〇〇無添加」と表示 |
このような10項目のルールにより、無添加表示はかなり厳密になりました。
ちなみに上記のルールは添加物の表示が義務付けられている、「容器包装された加工食品」に主に適用されます。
以下からは10項目のルールについて、さらに詳しく見ていきましょう!
①:単なる「無添加」の表示
無添加と表示する場合は、「〇〇無添加」と対象を限定しましょうというルールです。
理由は単に無添加と表示されていると、「何が添加されていないのか」が消費者にとって分かりにくいから。
たとえば以前は無添加の表示を見た消費者が「添加物が一切入っていない」と誤解して買ってしまうケースもありました。
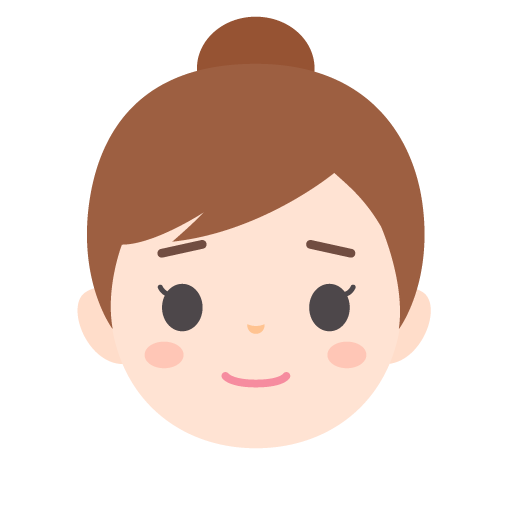
「無添加と書いてあったのに、よく見たら保存料が入ってる!」なんてことがあったんですね。
このような誤認を防ぐために、「保存料無添加」「着色料不使用」などと、何が無添加なのかを具体的に書くことになったんです。
今後、無添加食品を選ぶときは、「何が無添加なのか」をよく確認するようにしてみてください。
②:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
食品表示基準に規定されていない用語は、使わないようにしましょうというルールです。
具体的には人工・合成・化学・天然などの言葉が当てはまります。
理由はこういった言葉に対して、消費者が悪いまたは良い印象を持っていた場合に、商品の良し悪しを誤認する可能性があるから。
たとえば「天然の着色料なら大丈夫だろう」「合成保存料が入ってないなら安心だ」といった感じです。
国としては天然か合成かによらず、添加物の安全性を確認して使用を許可しているのだから、こうした印象を与えるのは良くないということなんですね。
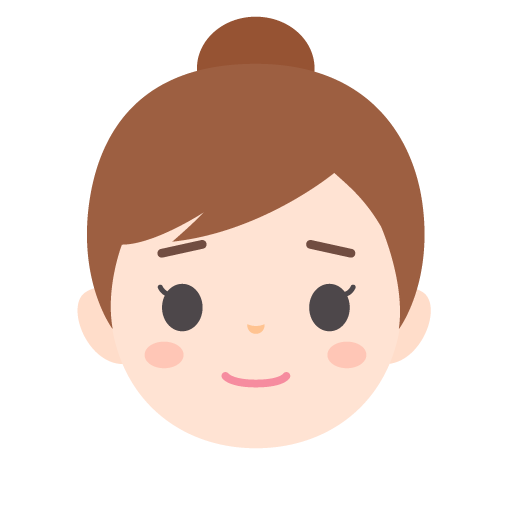
個人的には自然界に存在しない、化学合成された添加物はなるべく避けたいと思っているので、複雑な気持ちです。
私のように化学合成された添加物を避けたいと思っている方は、今後は自分で原材料欄をしっかりチェックしていく必要があります。
③:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
そもそも食品添加物の使用が認められていない食品に、無添加と表示するのは止めましょうというルールです。
理由は無添加表示のある商品のほうが、表示のない商品よりも優れたものだと、消費者が誤解する可能性があるから。
たとえば清涼飲料水にソルビン酸不使用と書かれていたら、「何か特別に良い商品なのかな?」と思ってしまうかもしれません。
しかし実際はソルビン酸は清涼飲料水での使用が禁止されているので、表示の有無に関わらず使われていません。
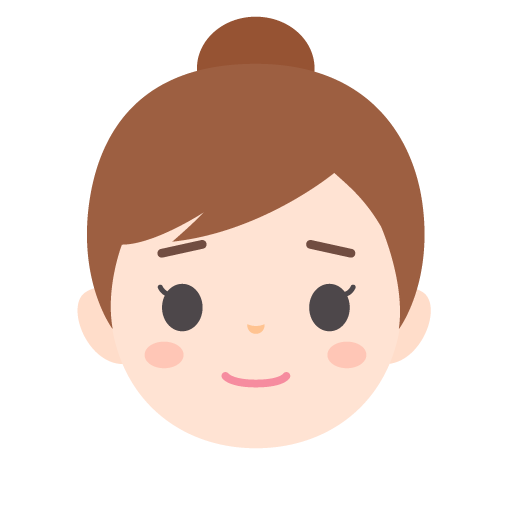
どのみち使われていないのに、表示の有無だけで商品の印象が変わってしまうのは良くないですよね。
当たり前のことをあえて書くことは、消費者に誤解を与える可能性があるので、禁止となりました。
④:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
同じような機能をもつ添加物を使っている場合は、無添加表示をしてはいけないというルールです。
たとえば「保存料無添加」と表示しながら、日持ち向上効果のある添加物・酸化防止剤を使っているケースなど。
この場合、実際は保存料に近いものを使っているのですが、そういった知識のない消費者はまったく使われていないと理解します。
それにより他の商品よりも良いものだと受け取る可能性があるので、禁止となりました。
⑤:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
同じような機能をもつ原材料を使っている場合は、無添加表示をしてはいけないというルールです。
たとえば「保存料無添加」と表示しながら、日持ち向上効果のある原材料・しらこたん白抽出物を使っているケースなど。
この場合、実際は保存料に近いものを使っているのですが、そういった知識のない消費者はまったく使われていないと理解します。
それにより他の商品よりも良いものだと受け取る可能性があるので、禁止となりました。
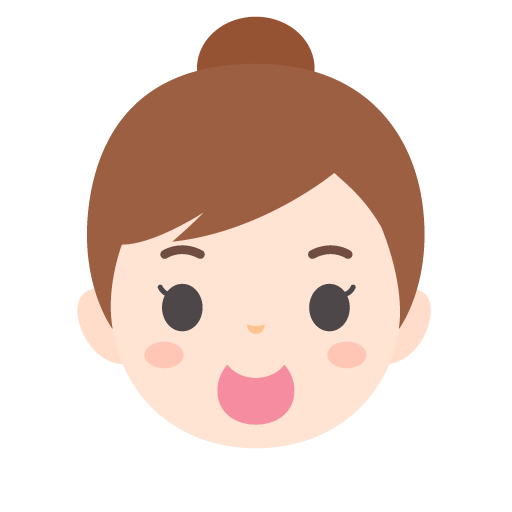
④⑤は似ていますが、要するに添加物だろうと原材料だろうと、同じような機能を持つものを使っているのに、無添加と表示してはいけないということですね。
⑥:健康、安全と関連付ける表示
「無添加=健康・安全」などの印象を与える表現を避けましょうというルールです。
なぜなら「無添加だから健康・安全」などの言葉は、添加物が悪いモノかのような印象を与えるから。
そもそも添加物は国が安全性を確認した上で使用を許可しているのだから、このような表現は不適切だということですね。
また無添加は必ずしも安全なのかというと、業者の衛生管理がいい加減だと、食中毒などを引き起こす可能性もあります。
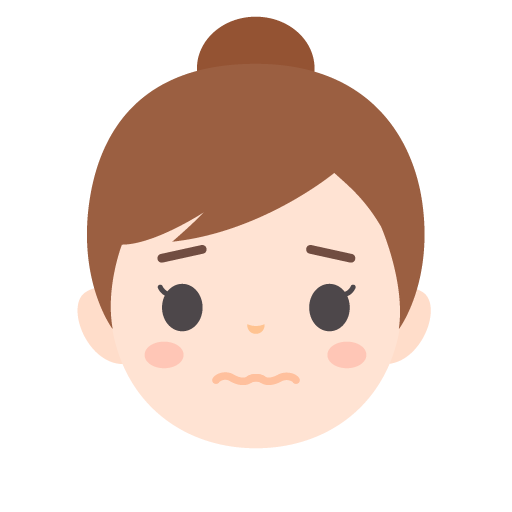
実際、販売業者の不衛生な管理が原因で、無添加マフィンによる食中毒が起きたこともありました。
このようなことから「無添加だから安全・健康」という表示は、消費者に誤解を与えかねないため禁止となりました。
⑦:効果・効能を連想させる表示をしないこと
健康・安全以外に、何らかの効果・効能がある印象を与える表現を避けましょうというルールです。
たとえば無添加だから美味しい、環境に優しいといった表示。
これらは無添加との因果関係や根拠をきちんと説明できない場合には、消費者に実際より良いものと誤解させる恐れがあります。
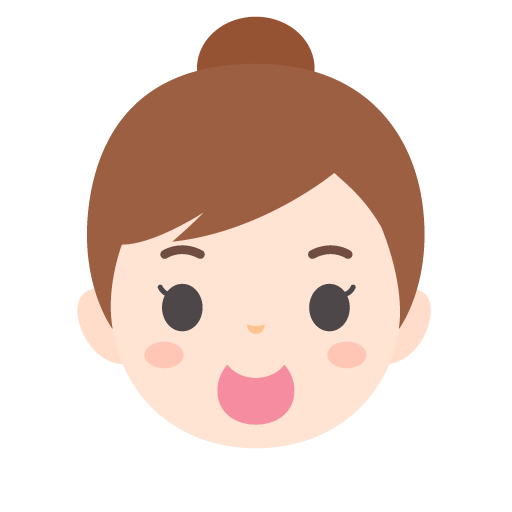
逆に言うと因果関係を説明できるなら、必ずしも禁止ではないということですね。
もし効果・効能をうたわれている商品があったら、因果関係がきちんと説明されているかチェックしましょう!
⑧:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
食品添加物が使われることのない食品に、無添加と表示するのは止めましょうというルールです。
たとえばミネラルウォーターに「保存料無添加」「着色料無添加」と表示するなど。
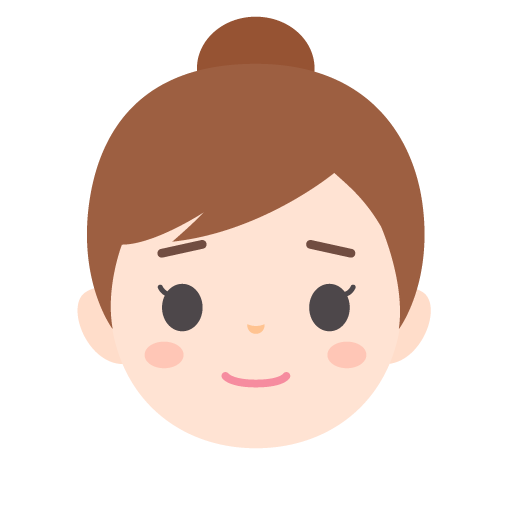
純粋な水であるはずのミネラルウォーターに添加物が使われることなんて、普通ありませんよね。
こういった食品にあえて無添加表示をすると、まるで他の商品には添加物が使われているかのような印象を与えます。
どのみち使われていないのに、無添加表示があるだけで、その商品が他より良いものと誤解される恐れがあるため禁止となりました。
⑨:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示
加工助剤やキャリーオーバーとして添加物が使用されている(または使用されていないことが確認できない)食品に、無添加と表示するのは止めましょうというルールです(※)。
ここで加工助剤・キャリーオーバーとは簡単に言うと、食品の原材料や加工の過程で使われる添加物のことです。
使用量が少なかったり、最終的に取り除かれたりすることから、原材料欄への表示が免除されています。
つまり、このような表示が免除される微量な添加物さえ使っていない場合にのみ、無添加表示を行いましょうということです。
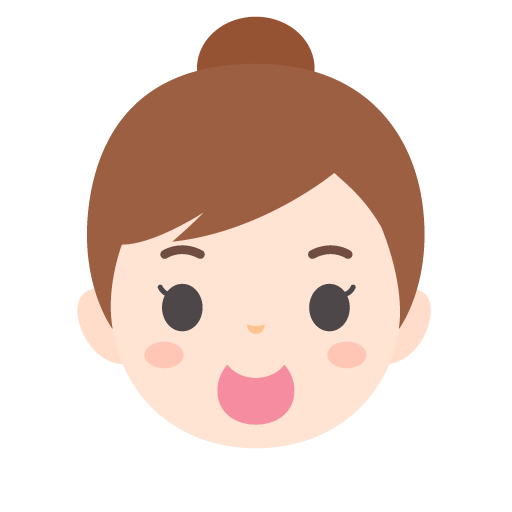
私が見てきた中でも加工助剤やキャリーオーバーまで気にしている業者は少なかったので、これはかなり厳しめのルールと言えます。
実質、無添加の定義とも言えるこのルールによって、無添加表示は以前よりずーっと厳密になったんですね。
※加工助剤やキャリーオーバーの添加物が「不使用であるか分からない場合」も、無添加と表示してはいけないということです。厳しいですね。
⑩:過度に強調された表示
無添加であることを、過度に強調して表示することは止めましょうというルールです。
たとえば商品のあらゆる場所に、過度に目立つ色やフォントで「〇〇無添加」と表示するなど。
理由は過度に強調された表示のせいで、消費者が実際以上に良いものと誤解する可能性があるから。
実際、あまりインパクトの大きい表示があると、それに目を惹かれて詳細な確認を怠ってしまうことがあります。
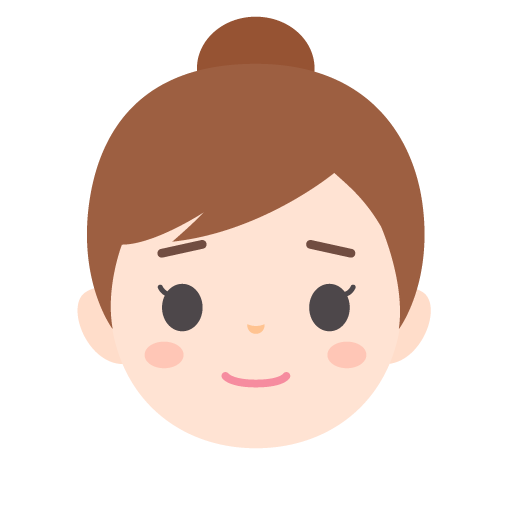
無添加とあったけど、よく見たら小さく「着色料」と書かれていて、ほかの添加物が使われていたなんてことも。
このような誤解を避けるために、過度な強調表示も避けることになりました。
まとめ:安全性の高い食品を見極める力を付けよう!
上記でお伝えしたとおり、2024年4月から無添加表示のルールが作られたことで、消費者に誤解を与えるような表示が禁止となりました。
より正確な情報を得やすくなったと同時に、今後は自分で原材料欄などをチェックして、無添加の食品を見極めていく必要があります。
最後にもう一度内容を確認しましょう!
1.無添加表示は禁止されたのか?
→禁止ではなく、ルールが厳しくなった
2.無添加表示が禁止された理由
→これまであまりにも消費者に誤解を与える、あいまいな表示が多かったから
3.無添加表示はどう変わったのか
→単に無添加と表記することや、効果をうたう表現、過度に強調されたデザインの禁止など、計10項目のルールができた
4.無添加表示の禁止による影響
→食品に使用されている添加物の正確な情報が得やすくなった
→今まで「無添加」の表示を頼りに食品を選んでいた人は、自分で原材料欄などを見て、使われている添加物を確認する必要が出てきた
今回の変化により、「今まで何となく無添加という言葉に惹かれて買っていた」という方は、どんな食品を選んだらいいのか分からなくなって戸惑っているかもしれません。
しかし添加物の表示ルールや避けたい添加物など、最低限の知識を身に付ければ、表示に頼らなくても自分で良し悪しを判断できるようになりますよ。
ひとまず以下の2つの記事を読んでおけば大体の知識は得られるので、よければ目を通してみてください。
また「自分で原材料欄などを確認するのは大変……」という方は、無添加にこだわる食品業者を利用するのもオススメです。
以下の記事では『無添加食品の宅配ランキング9選』を比較してご紹介しているので、よければチェックしてみてください!


